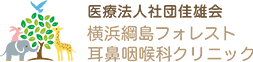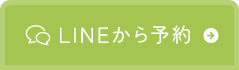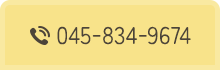めまいの症状(回転性のぐるぐる、浮動性のふわふわなど)
めまいの原因は大きく2つに分けられます。1つ目は耳の病気によるもの、2つ目は脳の異常を含んだその他の原因によるものです。耳鼻咽喉科疾患以外でめまいを起こす原因には、頭部外傷、脳腫瘍、脳底動脈循環不全、起立性低血圧、不整脈、自律神経障害、神経症、更年期障害、精神疾患なども考えられます。耳鼻咽喉科では、耳が原因で起こるめまいの診察を行っています。
めまいが発生すると、止まっているのに周囲がぐるぐる回っているように感じたり、ふわふわと浮いているような感覚になったりすることがあります。これは、目で見た情報と脳に伝わる情報が一致せず、体のバランスが崩れるためです。
めまいの多くは耳の最も奥にある内耳の異常が原因となっております。
当院では、バランスをみる重心動揺検査やめまいに伴う眼球の異常運動をみる眼振検査を行います。
めまいの患者さんはめまいが起こることが心配で安静を守りがちです。
安静にしすぎると三半規管が麻痺してかえってめまいが治りにくくなります。
治療としては頭を動かすような運動をお勧めしております。
良性発作性頭位めまい症
めまい疾患の中でもっとも多く、特定の頭の位置や頭を動かすこと(例えば寝返り、起床時、臥床時など)により誘発される回転性めまいです。めまいは数秒から数十秒でおさまり、難聴や耳鳴は伴いません。内耳にある耳石の一部がはがれて半規管(はんきかん)の中を浮遊し、頭の動きで移動するためにめまいが起こります。
このため運動療法によって浮遊耳石を細かくしたり、めまいを起こさない場所に耳石を移動させたりする治療が認められます。
その他めまいで考えられる病気
メニエール病
難聴、耳鳴、耳のつまり感などの聴覚症状を伴うめまいを繰り返す病気です。聴こえはめまいの前に悪くなり、めまいがよくなるとともによくなりますが、発作を繰り返すにつれて悪化していくケースもあります。時にはめまい、あるいは聴覚症状のどちらか一方だけが増悪を繰り返す非定型例もあります。この疾患は、意識消失、手足のしびれなど、脳の障害を思わせる症状を伴うことはありません。内耳のリンパ液が増加し、リンパ腔の圧力が上昇すること(内リンパ水腫)により症状が引き起こされますが、その誘因として種々のストレスが関与しているとも考えられています。
一般的にメニエール病は激しい回転性めまいのことと認識されておりますが、低音域難聴による片方の耳が塞がったような違和感を自覚した後、めまい発作を伴いめまいの軽快とともに耳閉感も変化するという疾患です。聴力検査にて一側性の低音聴力低下が認められることが多いです。
メニエール病の診断
診断および経過観察には、聴力検査と眼の動きを観察する眼振(がんしん)検査が必要となります。
治療としては内リンパ圧を下げるための利尿剤(イソソルビド)や漢方薬を使用いたします。めまい止め薬とともにその水を引く薬などを内服します。睡眠不足などによっても内リンパ液の吸収が悪くなるとされ、十分な睡眠に加え汗を流すような水分の代謝を活発にするような有酸素運動をして循環を良くすることや半身浴、サウナも効果があります。