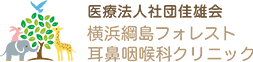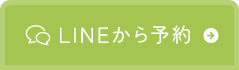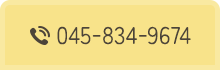においがわからない
(嗅覚障害)
 においがしない、食べた物の味が分からないといった症状は、嗅覚障害の可能性があります。
においがしない、食べた物の味が分からないといった症状は、嗅覚障害の可能性があります。
においがわからない
嗅覚障害とは
鼻の最上部、嗅裂(きゅうれつ)と呼ばれる場所に嗅上皮があり、その中にある嗅細胞に「におい分子」が到達すると、神経を介して脳でにおいを認知します。かぜやアレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症などで「におい分子」が嗅上皮まで到達できないと臭いがしなくなります。また、かぜのウイルスなどにより嗅細胞自体がダメージを受けると、しばしば高度の嗅覚障害となります。嗅覚の回復には、早期治療が重要ですので、においを感じられないなどお困りの症状があれば、当院までご相談ください。
嗅覚障害の症状
以下が、嗅覚障害の主な症状です。
- においが分からない
- においが以前より感じにくくなった
- 違うにおいがする
- わずかなにおいが強く感じる
- 全てのにおいが同じに感じられる
- 食べ物の味が分からなくなる
においがわからない時
(嗅覚障害)の検査・診断法
嗅覚障害の診断では下記に示すような診察や検査を行い、それらの情報をもとに総合的に判断します。
問診
 症状の詳細、発症のタイミングやその後の変化、異臭の有無、味覚の変化、喫煙の有無、既往歴、日常生活に支障が出ていないかなどを詳しくお聞きします。
症状の詳細、発症のタイミングやその後の変化、異臭の有無、味覚の変化、喫煙の有無、既往歴、日常生活に支障が出ていないかなどを詳しくお聞きします。
鼻内視鏡検査
 鼻腔内に約2mmの細いファイバースコープを入れ、におい物質の伝達の障害となる炎症やポリープ(鼻茸)などが発生していないか調べます。
鼻腔内に約2mmの細いファイバースコープを入れ、におい物質の伝達の障害となる炎症やポリープ(鼻茸)などが発生していないか調べます。
CT検査
副鼻腔に炎症や腫瘍などが発生していないか、鼻中隔湾曲や肥厚性鼻炎による鼻づまりの状態を確認いたします。
嗅覚障害の治療
嗅覚障害の治療の基本は原因となっている副鼻腔炎などの病気を治療することで、鼻の処置、投薬、手術などが行われます。
ステロイド点鼻、ビタミンB12製剤、亜鉛製剤、漢方薬が使用されます。
嗅覚障害に関する質問
匂いがわからないけど、味はわかるときは受診すべき?
嗅覚の低下は、風邪や花粉症といった身近な病気でも引き起こされることがあり、多くの人が経験するため、ついそのまま様子を見てしまう方も少なくありません。10日以上経過しても改善が見られない場合は、耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。
臭いがしない時は何科を受診すべき?
耳鼻咽喉科の受診がお勧めです。耳鼻咽喉科では、嗅覚障害だけでなく、においが感じられないために味も感じられなくなる「嗅覚性味覚障害」も確認できます。