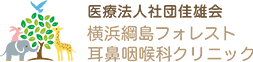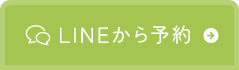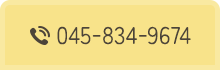補聴器・耳鳴り外来について
補聴器外来:毎週木曜日14時30分から16時
※毎週木曜日午後、補聴器・耳鳴り外来を行っております。はじめに一般外来を受診していただきます。新しく補聴器を購入予定の患者さんが対象となります。

聞こえが悪くなったと言われたりテレビの音が大きいとご家族から言われたり、病院の受付で名前を呼ばれても気付かなかったりすることがありませんか。
補聴器には抵抗があるかもしれませんが、難聴は認知症の危険因子にも挙げられていますので受診をお勧めいたします。
補聴器外来では、最初に耳や鼓膜の状態を確認し、聴力の検査を行い、治療が必要な疾患が隠れていないかをチェックします。耳垢が溜まっている、あるいは慢性中耳炎などが確認できた場合は、それらの治療を優先します。加齢性難聴のように治療で回復が難しいケースで、日常生活に支障をきたしている場合には、補聴器の導入を考える必要があります。
受診の目安
年齢を重ねるほど徐々に聴力は低下していきます。聴覚に関わる脳の機能を維持するためにも、聞こえにくいと感じたら早めに聴力の検査を受け、補聴器を使い始める適切な時期を考える必要があります。耳が聞こえにくくなり始めたら、早めにご相談ください。
補聴器とは
 補聴器とは、普通の大きさの声で話される会話が聞き取りにくくなったときに、はっきりと聞くための管理医療機器です。例えるなら小型の拡声器のようなもので、音をマイクロホンで拾い、電気信号に変換してから増幅し、イヤホンを通じて聞こえやすくしてくれる装置です。
補聴器とは、普通の大きさの声で話される会話が聞き取りにくくなったときに、はっきりと聞くための管理医療機器です。例えるなら小型の拡声器のようなもので、音をマイクロホンで拾い、電気信号に変換してから増幅し、イヤホンを通じて聞こえやすくしてくれる装置です。
会話の聞き取り状況の改善が目的
補聴器は、耳の聞こえが悪くなった方が会話やテレビ視聴など、様々な日常場面での聞こえにくさを改善するのが目的です。
補聴器を使用する際には、まずご自身の聴力状態を正しく把握し、日常生活でどのような状態で難聴を自覚されるか振り返ってみることが重要です。
難聴の度合いとライフスタイルや着用感など好みに合わせて選択
現在、市場には様々な種類の補聴器が登場しており、形状やサイズ、機能など多種多様です。補聴器により、高価で多機能なモデルもありますが、価格が高いからといって必ずしも全ての方に最適というわけではありません。難聴の度合いに合う補聴器を選択することや予算が優先されますが、自身の生活環境に合わせた着け心地や操作性、外観なども参考にしながら選ぶことが大切です。
補聴器の種類
耳かけ型
耳にかけて使用します。最近のものは外からは見えにくく操作性が良いことから選ばれることが多くなっています。最近では非常に小型の色彩豊かでおしゃれなデザインのものも多く見られます。症状が軽度の方から重度の方まで幅広く、聴力レベルに対応した製品が揃っています。
耳あな型
耳の中に収まります。そのため、小型の機種は目立ちにくいのが利点ですが、ボリューム調節ができないなど扱いにくく紛失しやすい欠点があります。
耳(耳介)の集音機能を活かせるのも特徴になります。一般的には、耳の形に合わせて型を取り、オーダーメイドで作られます。
耳かけ型補聴器と耳あな型補聴器では、電池式と充電式のいずれかを選択できます。
ポケット型
ポケットに本体を入れて使用します。イヤホンが本体とコードで繋がっています。最近では普及が減少しています。
診察の流れ

- 一般外来診療日に難聴を主訴に受診された患者さんに聴力検査を行います。
聞き取る能力を測定する語音明瞭度検査(語音弁別能検査)も後日行います。
検査結果より補聴器の視聴が必要であれば補聴器外来(毎週木曜日14時30分から16時)の予約をいたします。 - 補聴器には耳かけ型、耳あな型がありますが、視聴は耳にかけるタイプから開始いたします。まず、周波数測定器を使用して入力音を確認します。次に、補聴器の効果を比較するため、補聴器を外した時とつけたときの聴力検査(適合検査)を行います。その検査結果をもとに、患者さんの耳に適した音量に補聴器の音を設定します。その後、患者さんに補聴器を貸し出しいたします。長時間装用することによって脳が補聴器の音に馴れるため、なるべく長時間の補聴器使用を推奨しております。
- 2週間から1ヶ月に1回診察し、補聴器の調整をいたします。